2019年11月07日
北遠の庚申信仰⑪―阿寺の庚申仏
 上阿多古の東阿多古川を遡った山奥の集落、阿寺(あてら)のさらに奥、鴨野(かもの)の山の中腹に戸を閉ざされたお堂がありました。辺りを窺ってみると、縁の下の束石近くにどこかで見た記憶のある庚申石像が転がっていました。
上阿多古の東阿多古川を遡った山奥の集落、阿寺(あてら)のさらに奥、鴨野(かもの)の山の中腹に戸を閉ざされたお堂がありました。辺りを窺ってみると、縁の下の束石近くにどこかで見た記憶のある庚申石像が転がっていました。「これは、故米田一夫先生が、『遠州の野仏を追って』の中で紹介していた庚申仏に違いない。まさか、偶然にも巡り会えるとは・・・」。
画家である以前に詩人でもあった故米田先生が原稿用紙にしたためた文章を、生意気にも私がリライトして当時の「中日ショッパー」へ提稿。それを1冊にまとめたのが「ひくまの出版」から発行された『遠州の野仏を追って』でした。
その中で、米田先生は・・・
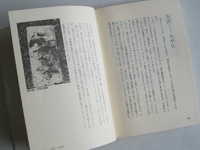 左沢というのは、山形県にある地名で、国鉄山形駅から出ている左沢線の終着駅でもあります。
左沢というのは、山形県にある地名で、国鉄山形駅から出ている左沢線の終着駅でもあります。さて、この左沢をどのように読まれましたか?国鉄難読駅名の一つ、アテラザワです。それにしても左をなぜアテラと読むのでしょうか。この地方にも同じ発音の地名が、天竜市上阿多古の「阿寺」と鳳来町の「阿寺」と二つあります。
いずれも主要道から外れた山深い土地で、日の当たらない所という意味だとか、いろいろな説があります。「アテラ」を「アチラ」の転化とみる説もあって、右と書いて「カテラ」と読むところもあるではないかというのですが、これはおかしいです。自分の住んでいる村を「アチラ沢」などと呼ぶわけはないと思います。
そこで、両方の阿寺へ行ってみました。日当たりは決して悪いところではありません。ですから、「アテ」という言葉は樹木の日陰を向いた側面で成長悪く反りやすい部分を指すとか、作物に適さないやせ地のことを「アテ」と言うから、山の陰とか、日光の充分でない土地のことだというのも、少し違うようです。それに「アテ」と「アテラ」とは別の言葉だと私は考えます。
それよりも、上阿多古の阿寺では、道を尋ねる人家も無いまま村落を通りすぎて、なおもどんどん急坂を登り続け(そのため運転者に、二度とこんな所へは来ないと言われてしまったくらいです)とうとう山上の鴨野という部落まで行ってしまいました。そこの小さなお堂の前で、焼け焦げのある庚申石像を見つけたのです。
畑にでも行っているのか、あたりは無人の家ばかりで、話を聞くことはできませんでしたが、正月十五日のドンド焼きの火の中へ道祖神の石像を投げ込むという風習のある地方を知っています。厄病神が病気にかかる人の名前を記した帳面を道祖神に預けておくので、それを焼き捨てるためだというのです。(後略)(米田一夫著「遠州の野仏を追って」左沢―火中仏より)
 1枚目の写真が、まさに米田先生が紹介しておられた「焼け焦げのある庚申石像」。確かに、今でも「焼け焦げた」ような跡が残っています。
1枚目の写真が、まさに米田先生が紹介しておられた「焼け焦げのある庚申石像」。確かに、今でも「焼け焦げた」ような跡が残っています。幸運にも私は、お堂のすぐ下に住む人から話を聞くことができました。その答えは、「庚申様を焼いたなんていう話は聞いたことがない」との返事。30年以上も前に米田先生が抱いた疑問に、一定の結論が出たような気がします。
かつては、10数戸あったという家も、今ではわずかに4戸が残るのみ。毎年「ドンド焼き」で焼いたような新たな焦げ跡は見られませんでしたので、焦げ跡のようなものが残る庚申石像は、別の理由でここに放置されているのだろうと思います。
米田先生!こんな結論でよろしかったでしょうか?でも、鴨野では先生の面影と再会できたような気がしましたよ。元気だった、あの頃の米田先生に・・・。





